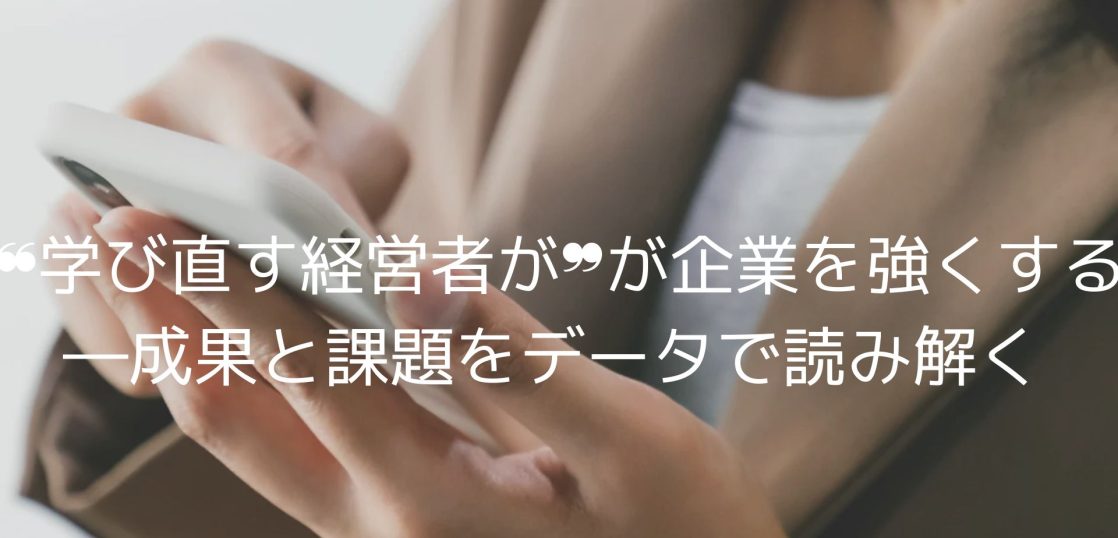中小企業経営者のリスキリング実態
昨今、❝リスキリング❞という言葉が注目されています。
リスキリングとは、❝学び直し❞という意味です。
「新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得する/させること」
これまでリスキリングといえば、主に転職者や従業員向けの言葉でしたが、経営者のリスキリングも「経営力や生産性向上、従業員の学び直し(人材育成)の後押しになる」と重要視されています。
一方、中小企業経営者は、プレイヤーとして多様な業務をこなすため、中々学ぶ時間がないという実態もあります。
そこで今回は、東京商工会議所が行った「経営者の学び直しに関するアンケート調査結果」から、共に他経営者の実態を見ていきましょう。
※全容はこちらをご覧ください。:東京商工会議所(2025).経営者の学び直しに関するアンケート調査.
経営者の学び直し7割が前向き
調査は、創業3年以上の東京商工会議所会員企業25,000社を対象に実施され、446社から回答がありました(回答率1.8%)。
回答企業のうち、従業員20人以下の事業所が58%と最も多く、製造業、サービス業、ソフト・ウェア・情報処理業、卸売業など幅広い業種から回答が寄せられています。
「学び直しに取り組んでいる」と回答した経営者は50%、
「取り組んでいないが2~3年以内に取り組みたい」が20%となり、
合わせて7割の経営者が学び直しに前向きな姿勢を示しました。
一方、「取り組んでおらず、取り組む予定もない」は22%にとどまっています。
これだけ見ると、取組み度が高そうに見えますが、調査の回答率が低いため、実際の取組み率はこの数値よりも低い可能性があると考えられます。
学び直しのきかっけは「不足スキルの取得」

学び直しの動機として最も多かったのは、
「事業を進める上で不足している知識やスキルを習得したかったから」(80%)。
次いで「新しい分野の知識やスキルに興味があったから」(56%)が続きました。
自発的な問題意識を背景とする学びが中心であり、外部からの働きかけによるものは少数でした。
学習手段としては、「書籍やWebサイトによる知識収集」(76%)が最多で、
「社外の勉強会・サークル等への参加」(56%)、「独学」(36%)が上位に挙がりました。
一方で、「公的機関での講座受講」(11%)や「eラーニング受講」(9%)といった公的支援の利用は限定的でした。

学び直しの課題として、現在取り組んでいる経営者・取り組んでいない経営者の双方で最も多かったのは「時間的な制約」でした。
取り組んでいる経営者では「費用負担が重い」(30%)、
取り組んでいない経営者では「現時点で必要性を感じない」(35%)、「何を学ぶべきか分からない」(32%)が主な理由です。
時間や費用面の課題に加え、学び直しの目的や内容を明確にすることの難しさも浮き彫りになっているようです。
学び直しに積極的な企業は「利益・新規事業」も好調
経営者が学び直しに取り組む企業は、そうでない企業に比べて利益が増加または維持傾向になる割合が高く、新規事業に取り組む割合も58%と高い結果が示されました。
また、経営者の年齢別にみると、若い世代ほど学び直しに積極的であり、特に40代以下では8割以上が取組みまたは意欲を示していました。
若い世代は、キャリアの初期段階にあり、自身の経営者としてのスキルセットを更新し、事業を次のステージに進めたいという思いが強いのかもしれません。
そして、学び直しはこの目標達成のための具体的なステップとなります。
また、SNSを通じて、最新の情報や学習コンテンツにアクセスしやすく、学びの機会を見つけやすいという傾向もあります。

経営者自身が学び直しを行っている企業では、従業員にも学び直しの機会を提供している割合が7割を超えました。
一方、経営者が学び直しに取り組んでいない企業では「提供していない」が多数を占めています。
また、従業員の学び直しを評価制度に反映する企業も一定数あり、
「資格・スキルを人事評価の基準にする」(49%)、「給与や賞与に反映する」(38%)などの回答が得られました。
経営者自身が学び続ける姿勢を見せることが、最も強力な❝教育文化❞となっているかもしれません。
おわりに
本調査では、経営者自身のリスキリングが企業の成長や従業員やの意識変化にまで波及している実態が明らかになりました。
学び直しを通じて経営を俯瞰し、将来の方向性を見つめ直す姿勢は、単なる知識習得にとどまらず、組織全体の価値観や風土の再構築にもつながっています。
学び直しが❝経営者の個人的な努力❞にとどまらず、❝企業の持続的な成長戦略の一部❞と位置付けられています。
一方で、時間や費用の確保といった現実的な制約、学びのテーマを選ぶ難しさなど、依然として課題は少なくありません。
こうした課題を解決していくためには、経営者同士のネットワークや、外部による情報提供の仕組みを充実させることが求められます。